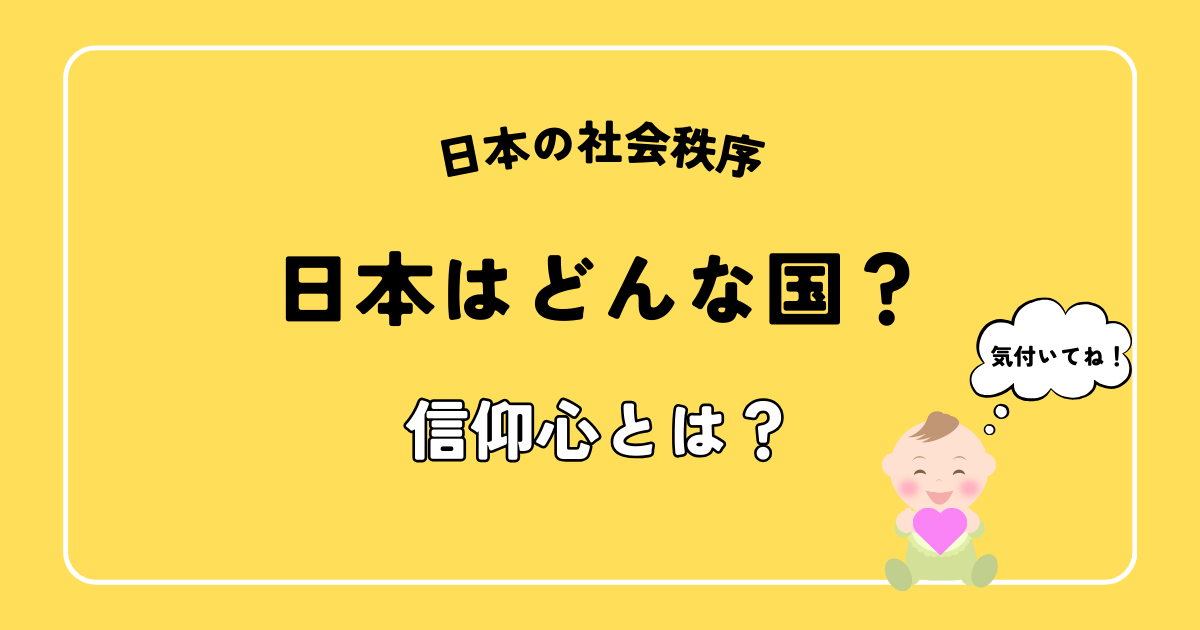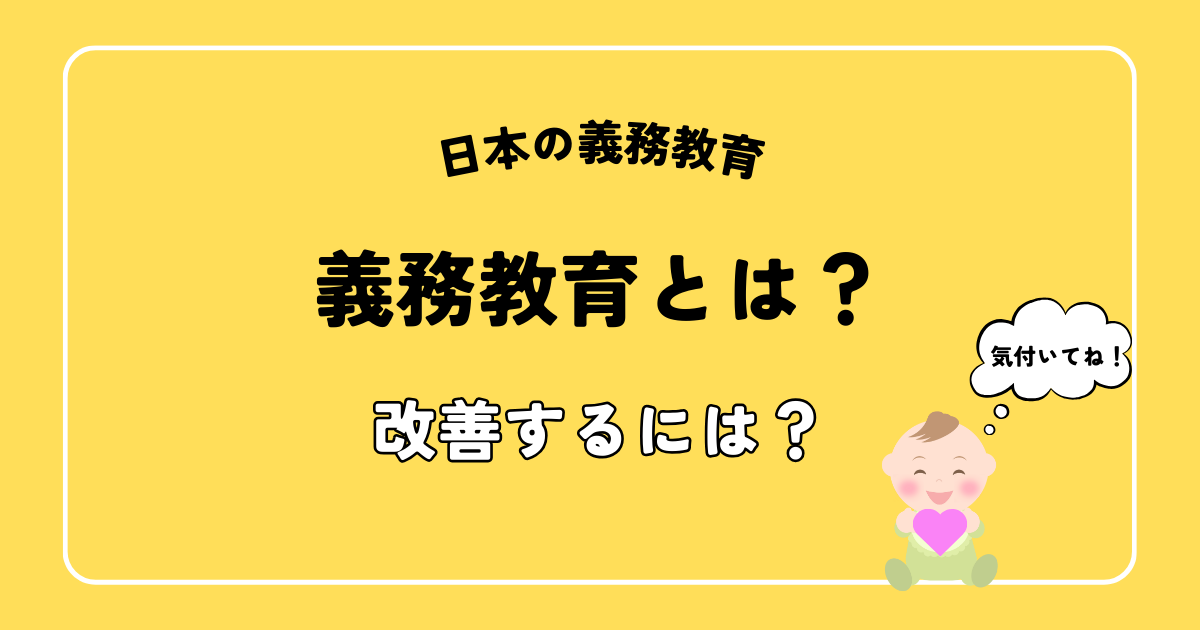日本社会、あるいは日本人を形成する背景には、何があるのでしょうか?
多くは、行事や遊び、義務教育、職場など、人と直接交流し、さまざまな環境の中で、教え伝えられてきた“文化”です。
日本に限らず、
海外や特定の地域でも同様に、
幼児期から人と交流し、接する中で、人それぞれが、教え伝えられてきたことがベースとなってその社会や文化を形成することになります。
海外の場合、さまざまな宗教による影響が多くなります。
日本では、
宗教の影響は無くはないのですが、
限定的な思考にとらわれないところが、海外とは異なります。
日本の時代背景としては、神道、儒教(儒学)、仏教、武士道、天皇制、太平洋戦争などの影響があります。
日本をひとつの文化圏としてとらえると、
多くの日本国民に共通して、
絶対的なものとしてでは無く、
祭りや年中行事などを通じて、
無意識のうちに、
信仰心というようなものが、
脈々と受け継がれてきたのではないでしょうか。
信仰心とは?
例えば神・仏など、
具体的に特定できる何かに限らず、
宗教などにも限らず、
ある神聖なものを信じ尊ぶことを意味します。
日本では、
無宗教の人が多いですが、
特定の宗教あるいは崇拝対象を限定することなく、
誰でも、
何となく、
信仰心が身につく環境で生育する、と言えそうです。
例えば、
神道(しんとう)は宗教ですが、
八百万神(やおよろずのかみ)など、崇拝対象を特に限定していません。
八百万神とは、数多くの神々の存在を総称して言うものです。
信心との微妙な違い
信心(しんじん)という言葉は、宗教的な考え方です。
信心とは、(仏や神など)すぐれたものを頼みとして、その力にすがること。
例えば、神仏に物事がかなうように祈願する、というような考え方や行動のことです。
何か達成したい目標があった場合、
達成するために一生懸命に努力をするよりも、
信心する行為に重点を置く傾向になり、
信心することこそが人を救う、
というような方向になりがちです。
視点を変えると、
例えば、
「信心したから○○○○出来た!良い結果になった!」というように、
何か達成できれば、
努力した結果、達成できたのに、
何でもかんでも信心のおかげにしてしまう、
非論理的な思考構造を構築する傾向になりがちです。
宗教関連の機関紙には、
結果と原因の因果関係について、
意味不明な記載が多く見られます。
信仰心以外の要素
いろいろ考えられますので、事例を書き出します。
和を以て貴しと為す
17条憲法は、西暦604年、日本で最初に文章化された法律とされています。
「和を以て貴しと為す」は、その第1条の条文です。
17条憲法は、指針となるような考え方を示した内容です。矛盾もありますし、その時代によって、条文解釈は幅広く変えて解釈できる内容になっています。
第1条だけを取り出して、
現代風に訳した例(以下、訳と原文はWikipediaから引用)としては、
「おたがいの心が和らいで協力することが貴いのであって、むやみに反抗することのないようにせよ。それが根本的態度でなければならぬ。ところが人にはそれぞれ党派心があり、大局をみとおしているものは少ない。だから主君や父に従わず、あるいは近隣の人びとと争いを起こすようになる。しかしながら、人びとが上も下も和らぎ睦まじく話し合いができるならば、ことがらは道理にかない、何ごとも成しとげられないことはない。」となります。
原文とされる第1条は以下の通りです。
「一に曰く、和(やわらぎ)を以て貴しと為し、忤(さか)ふること無きを宗とせよ。人皆党(たむら)有り、また達(さと)れる者は少なし。或いは君父(くんぷ)に順(したがわ)ず、乍(また)隣里(りんり)に違う。然れども、上(かみ)和(やわら)ぎ下(しも)睦(むつ)びて、事を論(あげつら)うに諧(かな)うときは、すなわち事理おのずから通ず。何事か成らざらん。」
日本の社会秩序
西欧諸国では、頻繁にデモが行われています。
訴える内容はさまざまですが、基本的にはさまざまな人権侵害について改善を求め、訴えています。
西欧では、領地が陸続きで、争いが絶えず、一般的構造として、弱肉強食の社会がベースですので、人権を市民が勝ち取って来たというような歴史があります。島国日本の場合、デモは比較的少ないのかもしれませんが、デモがあっても、社会的影響力のあるマスメディアがあまり報道しない傾向があります。
日本は、是非は別にして、激論を避け、“和”を大切にし、社会秩序を優先する傾向があります。→日本は民主主義?