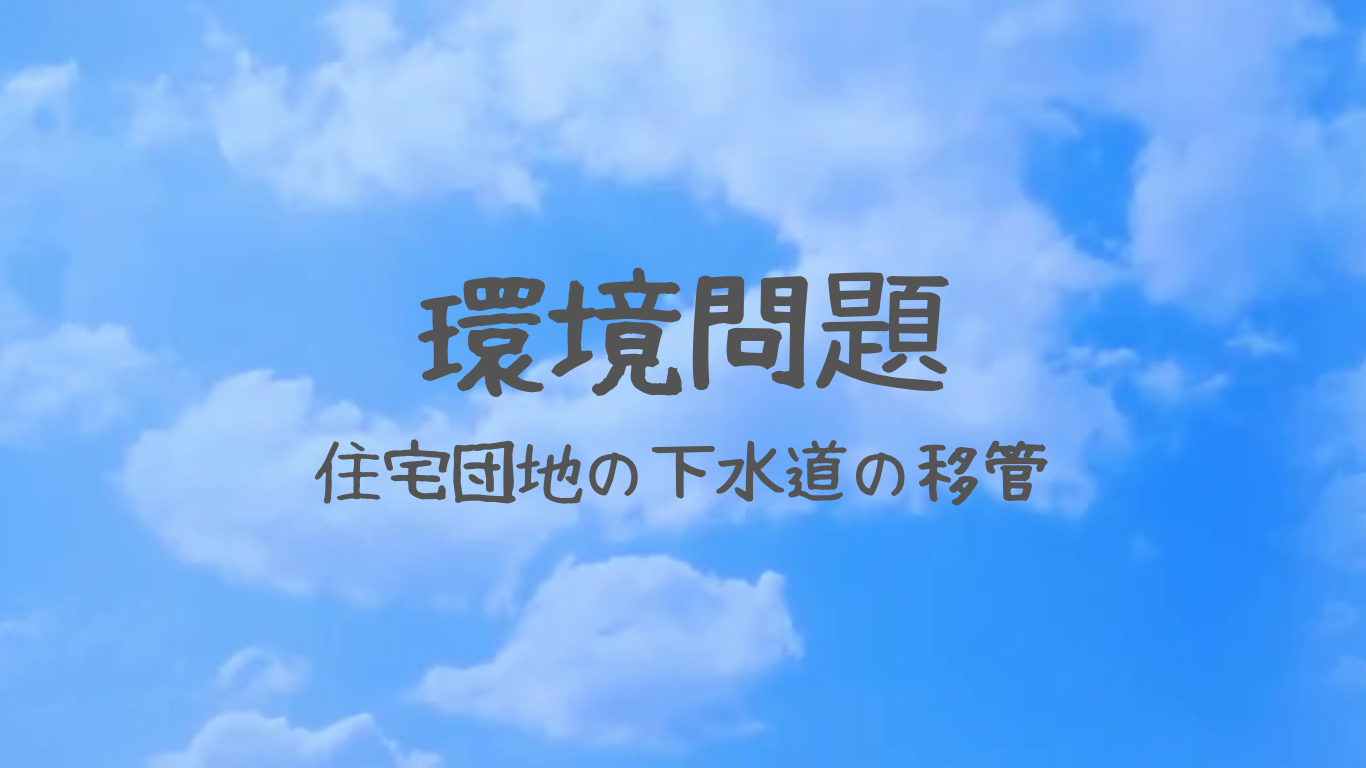住宅団地を造る場合、
広い土地を造成します(=開発行為)。
緑地・公園・車道・歩道・排水設備など、
秩序ある土地整備を造成事業者にさせなければなりません。
これらの開発行為は、
公共施設を設置する工事でもあり、
行政機関の許可が必要な制度として、
基本的には「都市計画法」1が適用されます。
このページの目次
はじめに
開発行為が許可されると、
公共施設は、
無償で、
不備なく整備(=建築基準法基準)されることになります。
住民は、
安心して入居し、
快適に生活できることになります。
法令基準を満たしていないと、
造成計画の許可2が出ませんし、
造成完了後に、住宅の販売が出来ません。
下水道の整備と移管について(法令の確認)
住宅には、廃水浄化設備が必要です。
生活排水を浄化せずに垂れ流すと、
環境を破壊してしまうからです。
したがって、
住宅団地には、
下水道3を設置しなければなりません。
都市計画法
「都市計画法」では、
下水道を
住宅団地に整備することが規定されています4。
下水道は、
法令の厳しい基準に従い、
無償で設置された公共施設(公の施設5)ということになります。
公共施設の管理者の同意等
公共施設とは、本来、地方公共団体の責任と費用で設置し、管理するものです6。
下水道の行政への移管手続
公共施設やその土地は、地方公共団体が所有するものです。
したがって、
新設される公共施設や敷地についても、
当然に、
民有地とするのではなく、
市町村が買い取る、
あるいは、
無償で移転するなどし、
所有権を移転する手続きをしなければなりません。
都市計画法は、移管手続について、細かく規定しています7。
行政が対応を誤った場合
行政は、すべて、法令に基づいて運営されます8。
法令に違反して処理した場合は、法令で、無効と規定されています。
移管交渉
裁判について
法令の確認訴訟について
損害賠償請求について
憲法
まとめ
- 「都市計画法」
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、都市計画の内容及びその決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第四条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
2 この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指定された区域を、「準都市計画区域」とは第五条の二の規定により指定された区域をいう。
12 この法律において「開発行為」とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行なう土地の区画形質の変更をいう。
第二章 都市計画
第一節 都市計画の内容
(都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)
第六条の二 都市計画区域については、都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする。 ↩︎ - 「都市計画法」
第三章 都市計画制限等
第一節 開発行為等の規制
(開発行為の許可)
第二十九条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「指定都市等」という。)の区域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。)の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
一 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの
2 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りでない。
「都市計画法施行令」
(許可を要しない開発行為の規模)
第十九条 法第二十九条第一項第一号の政令で定める規模は、次の表の第一欄に掲げる区域ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる規模とする。ただし、同表の第三欄に掲げる場合には、都道府県(指定都市等(法第二十九条第一項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。)又は事務処理市町村(法第三十三条第六項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。)の区域内にあつては、当該指定都市等又は事務処理市町村。第二十二条の三、第二十三条の三及び第三十六条において同じ。)は、条例で、区域を限り、同表の第四欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。
第1欄~第4欄
(法第二十九条第二項の政令で定める規模)
第二十二条の二 法第二十九条第二項の政令で定める規模は、一ヘクタールとする。 ↩︎ - 「下水道法」
第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠きよその他の排水施設(かんがい排水施 設を除く。)、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設(屎尿浄化槽を除く。)又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設、貯留施設その他の施設の総体をいう。 ↩︎ - 「都市計画法」
(定義)
第四条 この法律において「都市計画」とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
14 この法律において「公共施設」とは、道路、公園その他政令で定める公共の用に供する施設をいう。
「都市計画法施行令」
(公共施設)
第一条の二 法第四条第十四項の政令で定める公共の用に供する施設は、下水道、緑地、広場、河川、運河、水路及び消防の用に供する貯水施設とする。 ↩︎ - 「地方自治法」
第十章 公の施設
(公の施設)
第244条 普通地方公共団体は、住民の福祉を増進する目的をもつてその利用に供するための施設(これを公の施設という。)を設けるものとする。 ↩︎ - 「都市計画法」
(公共施設の管理者の同意等)
第三十二条 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。
2 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。
3 前二項に規定する公共施設の管理者又は公共施設を管理することとなる者は、公共施設の適切な管理を確保する観点から、前二項の協議を行うものとする。 ↩︎ - 「都市計画法」
(工事完了の検査)
第三十六条 開発許可を受けた者は、当該開発区域(開発区域を工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事(当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事)を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2 都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該工事が開発許可の内容に適合しているかどうかについて検査し、その検査の結果当該工事が当該開発許可の内容に適合していると認めたときは、国土交通省令で定める様式の検査済証を当該開発許可を受けた者に交付しなければならない。
3 都道府県知事は、前項の規定により検査済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域(津波防災地域づくりに関する法律第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域をいう。以下この項において同じ。)内における同法第七十三条第一項に規定する特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を除く。)に係るものであり、かつ、当該工事の完了後において当該工事に係る同条第四項第一号に規定する開発区域(津波災害特別警戒区域内のものに限る。)に地盤面の高さが同法第五十三条第二項に規定する基準水位以上である土地の区域があるときは、その区域を併せて公告しなければならない。
(開発行為等により設置された公共施設の管理)
第三十九条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第三十六条第三項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。ただし、他の法律に基づく管理者が別にあるとき、又は第三十二条第二項の協議により管理者について別段の定めをしたときは、それらの者の管理に属するものとする。
(公共施設の用に供する土地の帰属)
第四十条 開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第三十六条第三項の公告の日の翌日において当該開発許可を受けた者に帰属するものとし、これに代わるものとして設置された新たな公共施設の用に供する土地は、その日においてそれぞれ国又は当該地方公共団体に帰属するものとする。 ↩︎ - 「地方自治法」
第二条 地方公共団体は、法人とする。
② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
③ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
④ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
⑤ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
⑥ 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
⑦ 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
⑧ この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
⑨ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
⑩ この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
⑪ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
⑫ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
⑬ 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
⑭ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする
「行政手続法」
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。 ↩︎