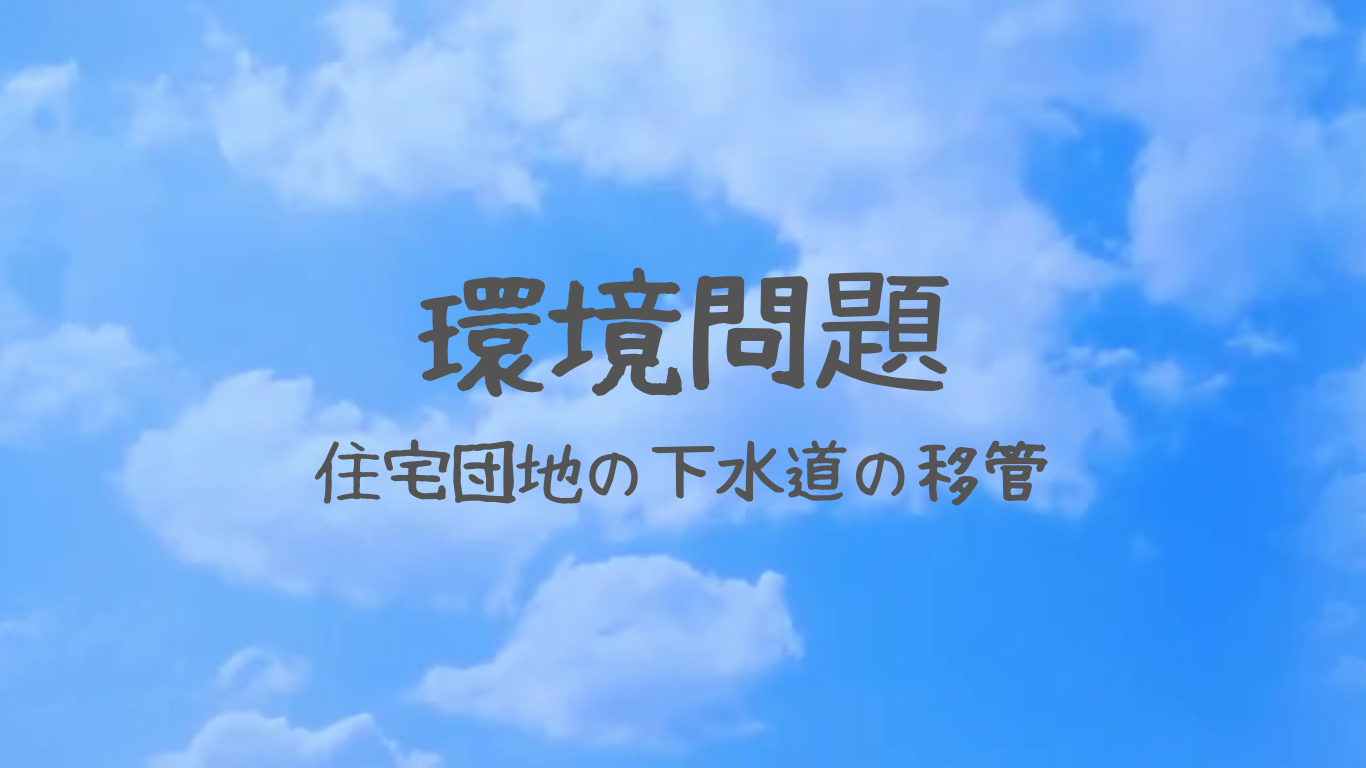行政は、すべて、法令に基づいて運営されます。1(=「地方自治法」第2条第2項、第16項、第17項など)
①4月4日付けで県に通報された文書に関連し、兵庫県が実施した処分について、
さらに、
②4月4日付文書について、適用される「公益通報者保護法」などの法令について、
詳しく検証します。
はじめに
マスコミなどの報道などでは、無記名で書いた3月12日付け文書を対象に、記事が書かれています。
兵庫県議会の「文書問題調査特別委員会」が調査の対象にしたからです。
しかし、
そもそも、
無記名で書いた3月12日付け文書は「公益通報者保護法」の対象にはなり得ません。
大手報道機関であれば、法律家と同じく、基礎的知識として理解されているはずです。
(詳しくは、「兵庫県知事選挙と公益通報者保護法(法律の適用)」をご覧ください。)
したがって、
このページでは、
無記名で書いた3月12日付け文書ではなく、
4月4日付通報文書について、
兵庫県が実施した処分や
適用される「公益通報者保護法」などの法令について記載します。
兵庫県の県職員に対する処分について
兵庫県は、4月4日付通報文書について、
兵庫県の人事当局が行った内部調査を基に、
文書の内容は核心的な部分が事実ではなく、誹謗中傷に当たると認定しました。
5月7日、当該文書を作成し流布した元県民局長に対して、停職3ヵ月の懲戒処分を決定しました。
第三者機関設置について
5月21日、兵庫県議会議長から知事に対し、県による第三者機関での調査実施の申入れがなされました。
第三者機関設置が決定し、第三者機関の事務の権限については、「地方自治法」第180条の22に基づき、代表監査委員に委任されることになりました。
監査委員の詳細は、兵庫県のウェブサイトから代表監査委員が誰かも参照できます。
兵庫県によると、
第三者機関による調査報告書は、2025年3月までに提出される見込みとのことです。
通報者について
職員は、4月4日、県の公益通報制度を利用し、庁内の窓口に疑惑を通報しています。
兵庫県は、5月7日、停職3ヵ月の懲戒処分を決定しました。
日本では、憲法で、誰でも、裁判を受ける権利が保障されています。
しかし、職員は、「公益通報者保護法」に反するとして、裁判所に訴状を提出していません。
兵庫県の対応 まとめ
兵庫県は、無記名で書いた3月12日付け文書、4月4日付通報文書の両方について、人事処分をしていることから、「公益通報者保護法」については、これらの文書が適用要件に該当しない、と判断していることになります。
県の対応に問題が無かったのか?について、詳しくは「兵庫県知事選挙の全容・まとめ」をご覧ください。
兵庫県議会の対応について
無記名で書いた3月12日付け文書は、上述のように「公益通報者保護法」の対象にはなり得ません。
しかし、議会は議題として取り上げ、「文書問題調査特別委員会」を設置しました。
適用される法令について
さまざまな法令について、検証します。
「公益通報者保護法」について
詳しくは、「兵庫県知事選挙と公益通報者保護法(法律の適用)」をご覧ください。
「公益通報者保護法」とは逆の規制をする法令について
ところで、
その法令で規定された内容と、
まったく逆の規制が、
別の法令で定められている場合があります。
今回の事案で、
まったく逆の規制とは、
服務規定違反です。
職員を保護する、というのではなく、
逆に、
職員の行為について処分(=「行政手続法」による処分)する、というものです。
具体的には、「地方公務員法」の服務規程(第30~38条)3違反の有無が問われます。
無記名で書いた3月12日付け文書も対象になり得ます。
他に参考までに、
類似した例として、
兵庫県を行政機関のひとつの組織としてみた場合、
日本という国も行政機関のひとつの組織です。
日本国という「国家」の場合には、
内乱に関する罪、あるいは外患に関する罪、というものが規定されており、「刑法」に犯罪として明文化されています。
具体的には、内乱に関する罪が「刑法」第77~80条4、外患に関する罪が「刑法」第81条、82条、87条、88条です。
ただし、
国ではなく
地方公共団体においては、
組織を転覆させるような重大な犯罪のような行為5であったとしても、明文化された犯罪・処罰規定はありません。
法令の分類について
法令の一番上位に位置するのが憲法です。
憲法が、国家の最高法規6です。
憲法の下に、
日本の場合、以下のさまざまな約2,000の法律が存在します。
「刑法」(刑事に関する法律)、
「民法」(民事に関する法律)、
行政法(あらゆる行政に関する膨大な数の法令の総称で、省令などの規則は毎日のように制定・改廃されています)があります。
「公益通報者保護法」は、行政法に分類されます。
裁判所が扱う事件について
裁判所が扱う代表的な事件は、民事事件、行政事件、刑事事件、家事事件、少年事件、医療観察事件があります。
行政事件とは、国や地方公共団体が行った行為に不服がある場合など,行政に関連して生じた争いを解決するための手続に関する事件です。今回の事案が該当します。→出典:裁判所
まとめ
4月4日付文書に適用される法令は、さまざまな視点で考察する必要があります。
法令は、
さまざまな行為に対して適用されるものですが、
詳細な要件を検証する必要があるため、終局的な判決として結論を出せるのは裁判所だけです。
終局的結論として、
裁判になることを想定すると、
申し立てをする方も、相手方になりそうな方も、自身で、さまざまな要件について、十分な検証をするはずです。
結果として、
裁判に訴えないケースや、判決に至るケース、裁判途中で和解するケースなど、さまざまなケースが考えられます。
裁判というものは、
誰でも裁判を受ける権利が保障されていますが、
終局的結論を見据えると、上述のように、安易に裁判に至るものではないはずです。
法令に基づく終局的判断、
つまり裁判は、
基本的には当事者の問題であって、
当然に、
議員や議会など、第三者が立ち入ることが出来ない制度ということです。
- 「地方自治法」
第二条 地方公共団体は、法人とする。
② 普通地方公共団体は、地域における事務及びその他の事務で法律又はこれに基づく政令により処理することとされるものを処理する。
③ 市町村は、基礎的な地方公共団体として、第五項において都道府県が処理するものとされているものを除き、一般的に、前項の事務を処理するものとする。
④ 市町村は、前項の規定にかかわらず、次項に規定する事務のうち、その規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものについては、当該市町村の規模及び能力に応じて、これを処理することができる。
⑤ 都道府県は、市町村を包括する広域の地方公共団体として、第二項の事務で、広域にわたるもの、市町村に関する連絡調整に関するもの及びその規模又は性質において一般の市町村が処理することが適当でないと認められるものを処理するものとする。
⑥ 都道府県及び市町村は、その事務を処理するに当つては、相互に競合しないようにしなければならない。
⑦ 特別地方公共団体は、この法律の定めるところにより、その事務を処理する。
⑧ この法律において「自治事務」とは、地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のものをいう。
⑨ この法律において「法定受託事務」とは、次に掲げる事務をいう。
一 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第一号法定受託事務」という。)
二 法律又はこれに基づく政令により市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、都道府県が本来果たすべき役割に係るものであつて、都道府県においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの(以下「第二号法定受託事務」という。)
⑩ この法律又はこれに基づく政令に規定するもののほか、法律に定める法定受託事務は第一号法定受託事務にあつては別表第一の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に、第二号法定受託事務にあつては別表第二の上欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりであり、政令に定める法定受託事務はこの法律に基づく政令に示すとおりである。
⑪ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づき、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえたものでなければならない。
⑫ 地方公共団体に関する法令の規定は、地方自治の本旨に基づいて、かつ、国と地方公共団体との適切な役割分担を踏まえて、これを解釈し、及び運用するようにしなければならない。この場合において、特別地方公共団体に関する法令の規定は、この法律に定める特別地方公共団体の特性にも照応するように、これを解釈し、及び運用しなければならない。
⑬ 法律又はこれに基づく政令により地方公共団体が処理することとされる事務が自治事務である場合においては、国は、地方公共団体が地域の特性に応じて当該事務を処理することができるよう特に配慮しなければならない。
⑭ 地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。
⑮ 地方公共団体は、常にその組織及び運営の合理化に努めるとともに、他の地方公共団体に協力を求めてその規模の適正化を図らなければならない。
⑯ 地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。
⑰ 前項の規定に違反して行つた地方公共団体の行為は、これを無効とする。
「行政手続法」
(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例及び地方公共団体の執行機関の規則(規程を含む。以下「規則」という。)をいう。 ↩︎ - 「地方自治法」
第五款 他の執行機関との関係
第百八十条の二 普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の委員会又は委員と協議して、普通地方公共団体の委員会、委員会の委員長(教育委員会にあつては、教育長)、委員若しくはこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員に委任し、又はこれらの執行機関の事務を補助する職員若しくはこれらの執行機関の管理に属する機関の職員をして補助執行させることができる。ただし、政令で定める普通地方公共団体の委員会又は委員については、この限りでない。 ↩︎ - 「地方公務員法」
(服務の根本基準)
第三十条 すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、且つ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第三十一条 職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。
(法令等及び上司の職務上の命令に従う義務)
第三十二条 職員は、その職務を遂行するに当つて、法令、条例、地方公共団体の規則及び地方公共団体の機関の定める規程に従い、且つ、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第三十三条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(秘密を守る義務)
第三十四条 職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表する場合においては、任命権者(退職者については、その退職した職又はこれに相当する職に係る任命権者)の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は、法律に特別の定がある場合を除く外、拒むことができない。
(職務に専念する義務)
第三十五条 職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。
(政治的行為の制限)
第三十六条 職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2 職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の区若しくは総合区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区若しくは総合区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
一 公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
二 署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三 寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四 文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
五 前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
3 何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4 職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5 本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。
(争議行為等の禁止)
第三十七条 職員は、地方公共団体の機関が代表する使用者としての住民に対して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。又、何人も、このような違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおつてはならない。
2 職員で前項の規定に違反する行為をしたものは、その行為の開始とともに、地方公共団体に対し、法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程に基いて保有する任命上又は雇用上の権利をもつて対抗することができなくなるものとする。
(営利企業への従事等の制限)
第三十八条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。ただし、非常勤職員(短時間勤務の職を占める職員及び第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員を除く。)については、この限りでない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。。 ↩︎ - 「刑法」
(内乱)
第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
(予備及び陰謀)
第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。
(内乱等幇助)
第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。
(自首による刑の免除)
第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
第三章 外患に関する罪
(外患誘致)
第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。
第八十三条から第八十六条まで 削除
(未遂罪)
第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。
(予備及び陰謀)
第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 ↩︎ - 【兵庫県議会】令和6年9月6日午前 文書問題調査特別委員会(百条委員会) 片山元副知事の答弁
「メール調査の報告が、人事当局から上がってきましたが、その中には、『クーデターを起こす、革命、逃げ切る』こういうくだりがありました。」 ↩︎ - 「日本国憲法」
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
② 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 ↩︎