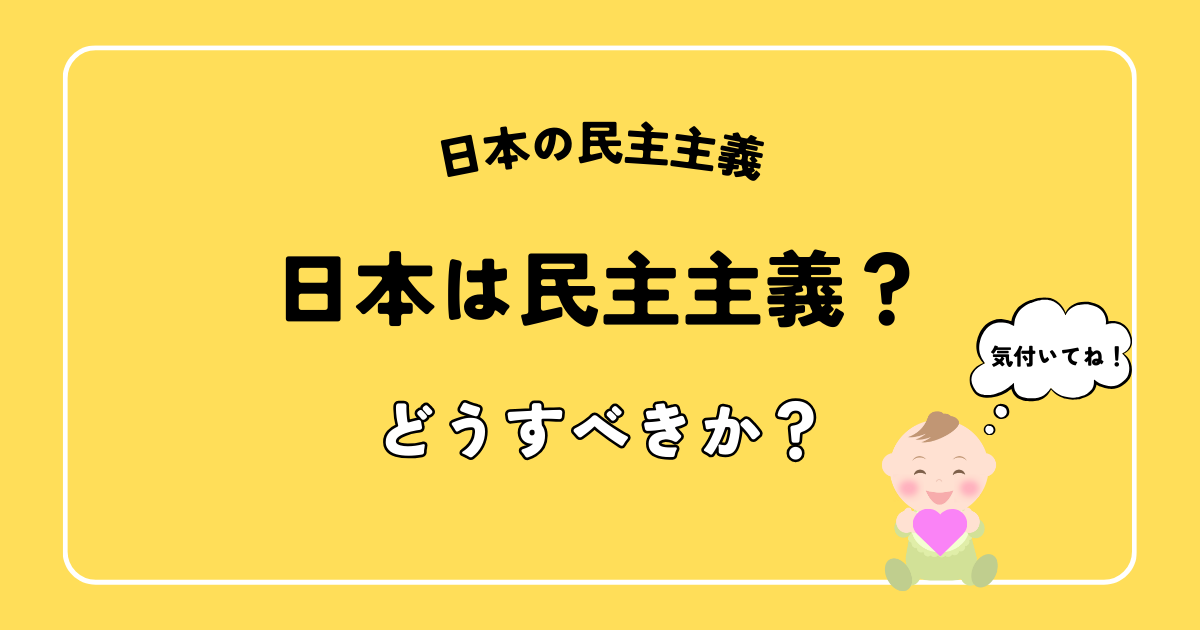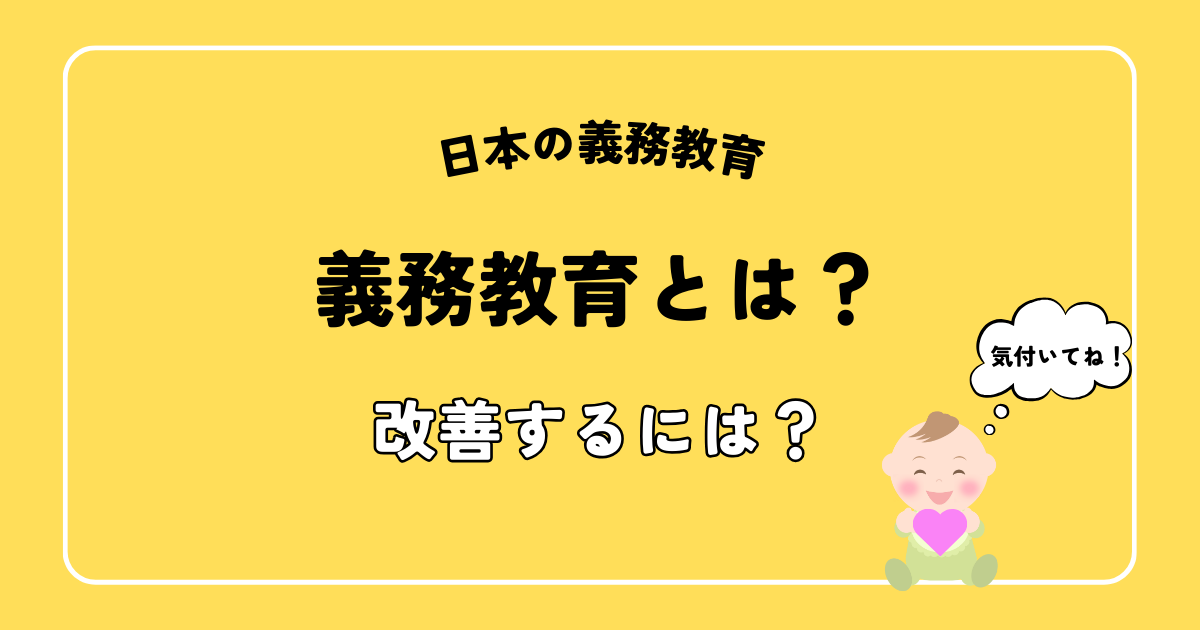日本は、民主主義国家の一員です。
民主主義の基礎となるのは、議論です。
ただ、
日本の義務教育では、
議論について、
実践して体験する機会がありません。
はじめに
日本では、
義務教育を終え、
社会に出ても、
和やかな地域社会や
上意下達の職場では、
議論の重要性が軽視され、
議論を避ける社会的傾向が強く、
秩序を優先した付き合い方が主流になります。
日本の現状とは?
日本では、
生涯を通じて、
どんな状況であっても、
和を大事にするあまり、
「仲良くしなさい!」と保護者が子供に言うような、
つまり、
あえて議論しない、
課題を放置するような環境が継続します。
したがって、
実質的に日本では、
民主主義というにはほど遠い
社会の仕組み・政治体制が形成されています。
社会秩序を優先する、
「本音と建前の社会」が良しとされるような社会なのです。
結果として、
課題を共有して解決し、
進化・発展する機会を失っているケースが多いのです。
一体、どういうことなんでしょうか?
これは、“単純なこと”のひとつでもあります。
人というものは、議論しないと、気付かないことが多過ぎて、進化・発展できないものなのです。
詳しくは、“単純なこと”をご覧ください
民主主義とは?
民主主義とは、組織が意思決定する際に、組織を構成する者が最終決定権(主権)を持つという制度です。
制度には、直接民主制や間接民主制など、さまざまな形態があります。
民主主義社会では、
何かを重要事項を決める場合、
十分な議論が尽くされることを前提に、構成員が相手の主張内容の理解にたどり着いたり、中庸案などでまとめるように調整したり、多数決で決めたり、さまざまな決め方を選択できます。
勘違いや間違いをする人、
完全ではない人にとって、
議論を前提にする制度は、
進化・発展のためには、必要な仕組みです。
国家体制によって異なる「民主主義」
某テレビ番組で、日本、米国、中国のそれぞれ10人程度の学生が討論し、すべての学生が、自国について、「民主主義国家である。」と、考え方を披露する場面がありました。多くの方は、「なぜ中国が?」と思われるかもしれませんが、国家から強制された発言ではなく、彼・彼女たちの本心からの発言、と理解する必要がある様です。(代表者会議を開催しているというような主張ですが、閉鎖的な一部階層による会議が開催されている状況などのため、民主主義指数、自由度の指数などの指標からは、中国は民主主義国家ではない、と一般的には評価されそうです。)
一方で、
日本の選挙の投票率の低さは、選挙権を行使しない「日本は、本当に、民主主義なのか?」と疑われるかもしれません。
議論の始まり
議論は、一般的には気付かれていない課題を解決し、改善(進化・発展)するために行われます。
このため、議論の提案者も聴く側も、課題について、十分な理解をしていない段階で始まるのが普通です。
曖昧な状況から議論を始める場合でも、正確な現状把握を基礎として議論すると、建設的な議論に発展します。
とにかく、
議論は、完全ではない人にとって、課題解決や進化・発展のために必要な手続きです。
視点を変えて、
インターネット上で、SNSで、180度異なるやり取り、とんちんかんな絡み、「馬鹿か?」と思われるような発信が乱れ飛ぶのは、正確な現状把握(=理解)が出来ていないのに発信しているからです。とんちんかんな発信者は、自分がまだ理解できていない状態のまま発信していることに気付いていません。もし、自分が理解できていないことに気付いていれば、発信する内容は疑問形になるはずです。なので、まずは、分からないことを質問するはずです。ところが、分かっていなくても、断定形で堂々と発信してしまう。世の中には、かなり高い確率でそんな方が存在します。
よくあるパターンとしては、
議論の提案者は課題に気付いているかも知れない状態です。勘違いや間違いの可能性もありますが。したがって、傾聴する方は、相手の身になって、まずは質問形で現状把握をしてから、議論に入る必要があります。ところが、お互いに断定形で発信・返信してしまう。そうすると、議論では無く、言い争いになってしまいます。
正確な現状把握が出来ない人、勘違いや間違いを堂々と発信していることに気付いていない人が多いのです。
インターネット上やSNSに限らず、公の場での事例も同様です。
例えば、
2024年の兵庫県知事選挙では、
(=「兵庫県知事選の全容・まとめ」をご覧ください)
誠実そうな人物や組織、大手マスメディアでさえ、
不正確な情報を発信し、
修正もしない実情が明らかになりました。
“単純なこと”ですが、
報道機関は、
いったん報道した内容について、
軽々しくは、修正し難く、
SNSは、
発信内容を気軽に修正し易い、
というのが実際です。
また、
誠実そうな人でも、
有名なマスメディアでも、
秀才や天才の集まりとは限らない、
人がすることには、
勘違いや間違いがある、
ということを理解する必要があります。
知事選挙の事例で、
明らかになったことは、
新聞やテレビだけではなく、
インターネットを含め、
情報源は広く持ち、
自分自身で、
正確な情報を探究して、
適切に現状を把握し、
物事を判断しなければならない
という“単純なこと”です。
議論の進め方
難問を議論する場合には、
どんな組織でも、
家庭内でも、
課題について、
共通認識(=単純なこと)を共有しながら進めると、
問題点を明確にし、
改善策を明文化(文章化)出来るため、
解決することが出来ます。
ファシリテーション
和や秩序を大事にするあまり、
いろいろな発言を制限して平穏無事にまとめようとするのが良いのか?
意見が出易い、意見が出尽くす仕組みや環境を作った方が良いのか?
勘違い、間違いが多い人間社会では、
後者の方が、進化発展する可能性が高くなります。
ファシリテーション(=集団で問題や課題を解決するために、認識を一致させたり、相互理解を促したりするサポートのこと)をするファシリテーターの存在意義がそこにあります。
民主主義の基礎となる議論は、
誰かが、何かに気付いたところから始まりますので、
議論の提案者でさえ、
認識や理解が不十分なのは当然のことです。
なので、
ファシリテーターが不在の場合、
少々激論になってはじめて議論に到達することになります。
日本の民主主義は、
「日本はどんな国?」で書いたように、
和を大事にするあまり、
ファシリテーターが不在の場合には、
「議論の始まり」に書いたように、
議論にまではなかなか到達しない文化なのかもしれません。
義務教育に議論の実践が必要な理由
日本文化を批判したり、
変えたりする必要はありません。
しかし、
日本社会が進化・発展するためには、
議論について、理解とスキルを習得する必要があります。
オープンな議論が基本
非公開の秘密会議や
一部関係者に限った話し合いは、
議論であって議論でない要素が多いものです。
例えば、
中国やロシアや北朝鮮でも議会は設置されています。
議論のテーマの内容によっては、
個別具体的に、
議論の進め方を検討する必要があります。
仮に、
秘密会議の必要性があるという意見が出た場合には、
議論としては異例な形式になりますので、
その議論は、議事録に記録する必要があります。
激論の体験
「ファシリテーション」で記載したように、
少々激論になってこそ、
はじめて適切な議論に到達することを
義務教育の期間中に体験しておく必要があります。
ファシリテーターの育成・体験
また、
激論に至らないで、
議論を円滑に進めるためには、
ファシリテーターの育成や体験も義務教育として必要です。
日本社会の進化・発展のため
議論できない社会は、
進化・発展できないため、
“気付かない”社会的損失、
日本国としての損失が大きいのです。
何を目的に義務教育制度を設けているのか?
原点に立ち返る必要があります。
国難の時代、日本に必要な議論
戦争に猪突猛進した時代には、
振り返ると、
新聞などのメディアが、
非論理的な主張で読者を扇動し、
多くの国民が、
まともな議論が無いまま、
情報を取捨選択する能力もなく、
とんでもない方向を「良し!」として、
戦争に向かっていった事実があります。
戦後の高度経済成長期には、
何もない状態からのスタートでしたから、
立ち止まって考える必要もなく、がむしゃらに、
一生懸命努力すれば、金銭的には、報われた時代です。
高度経済成長期には、、
議論を尽くして、
最善策を模索する必要が無かったのかもしれません。
しかし、現在の日本は、
少子高齢化で、
国内では、物の消費量が減り続け、
かつて日本の輸出販売先であった諸外国は、
日本のように進化・発展したため、
日本からの輸入に頼らずとも自国生産できる商品が増え、
自給自足できる割合が増えたため、
日本で生産した商品は、海外での販売先を減らしています。
日本の経済事情は、
日本人による内需拡大に期待できない状況で、
外国人旅行客のインバウンド需要などに頼らざるを得ない時代です。
日本の現在の経済事情では、
国民から徴収した貴重な税収の使い道について、
議論を避けるのではなく、
まともな議論をして、
財政支出を“やり繰りする”のが必須の時代なのです。
立法府や地方議会(=議員)には必須の法令の理解
議論して、改善策が明確になれば、文章や条文で明文化し、記録にまとめたり規制したりする必要があります。
ここで、文章化する能力を備えていないと、具体的な改善策を明確にすることが難しくなります。
議論して、問題を解決できると、最終的には、改善策を文章で具現化することになるからです。
文章化する能力とは、日本語の読解能力です。
なお、
法令の理解とは、
法令の構造、条文の読解力、要件、比較衡量、行為を具体的な文章に置き換える能力など、が必要ということです。
(詳しくは、別のページに書きます。)
兵庫県知事選挙の経緯からは、県議会議員の法令の理解の程度が明らかになりました。(「兵庫県知事選の全容・まとめ」をご覧ください)
終わりに
議論のスキルというものは、
人の成長に伴って、
自然に身につくようなものではありません。
したがって、
義務教育の期間に、
実際に議論する機会を設けて、学習する必要があります。
義務教育とは、
文部科学省によると、
国民が、
共通に身に付けるべき公教育の基礎的部分を,
だれもが等しく享受し得るように制度的に保障するもの。
なので、
民主主義国家の基礎となる議論を体験する機会は、
義務教育のカリキュラムには、当然のこととして、必要なのです。
先生による「教育」は、
生徒よりもはるかに高度に認識・理解している内容を
生徒に学習させる作業です。
ただし、
先生も人ですので、
勘違いや間違いが無いとは限りません。
逆の視点で、
大人でも、
やはり人ですので、
育児で「子供に教えられた」ことは、あるはずです。
例えば、
2024年の兵庫県知事選挙に至る経緯は、
有権者から負託を受けた議員、
時には“先生”と呼ばれることもある議員、
行政機関(都道府県職員)に一目置かれる議員、
いわば、
指導的立場のような人たちが間違ってしまった事例です。
動画で公開されている文書問題調査特別委員会での議論は、
議論の一部を除くと、
適切な議論が出来たのか?
極めて疑問です。
知事を失職に追いやった兵庫県議会の議論について、
議論の内容、
プロセス(進め方)、
決め方など、
適切だったのか?
極めて疑問です。
一部のマスメディアについては、
いまだに、
現職の兵庫県知事を批判する偏向報道を
かつての
「戦争やむなし」報道を彷彿させるような
非論理的な報道を“現に”継続しています。
恐ろしい状況です。
読者には、
(議論のベースになる)論理的思考を身に付け、
情報を取捨選択する能力が求められています。
“有権者に選出された議員の資質”の問題は、
投票する有権者の資質が問われているのと同じで、
社会人の教育問題にもつながります。
これらの問題は、
根本的な原因を改善するためには、
将来の有権者の義務教育をどうすべきか?につながります。
更に、
兵庫県議会が、
議論や結論の方向性を間違えた原因は、
論理的思考の欠如だけでなく、
法令の理解の欠如、
哲学的思考の欠如にあるのでは?と考察できそうです。